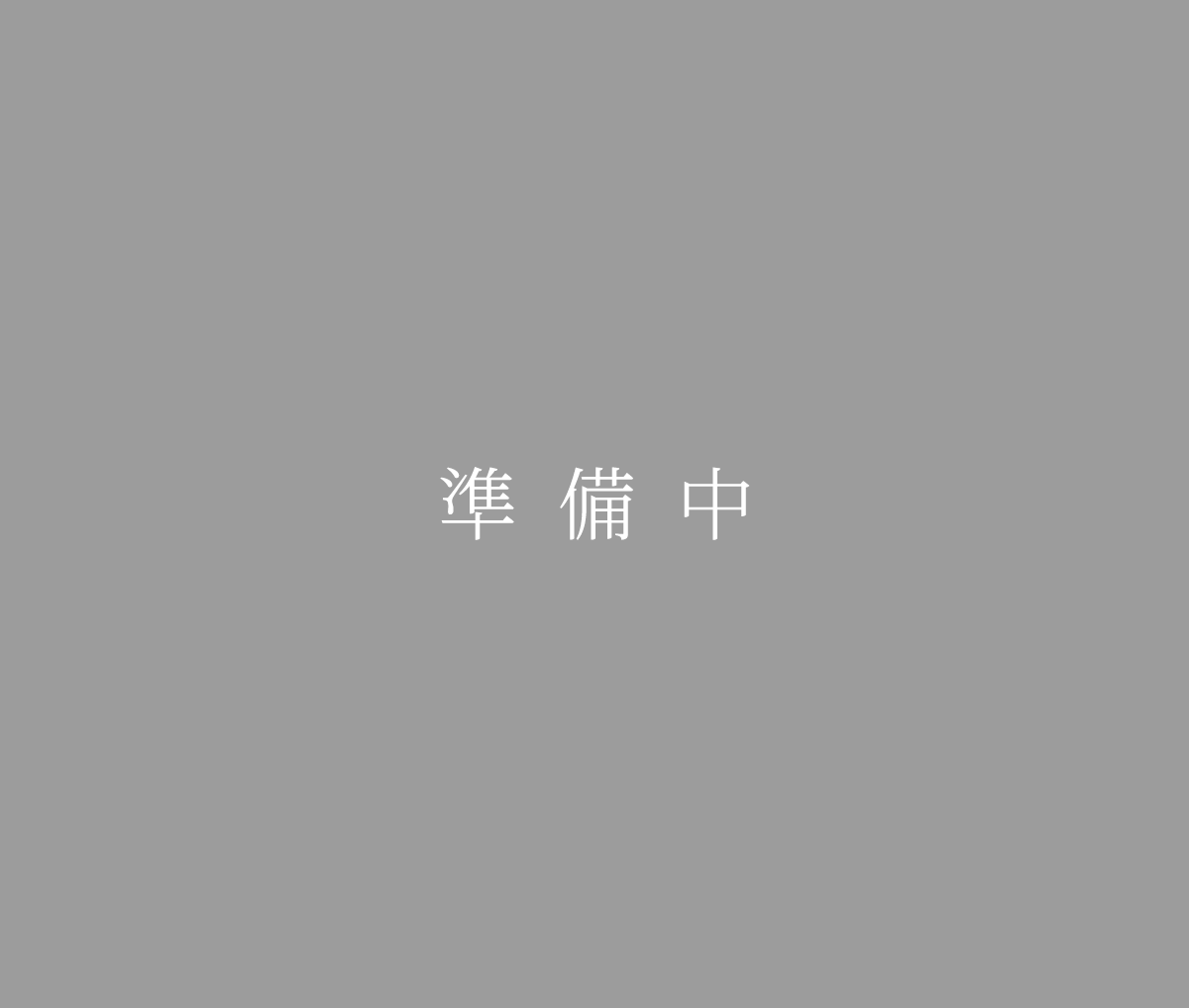腎臓内科とは
腎臓内科は、腎臓の働きが低下することで起こる病気や、慢性腎臓病(CKD)、高血圧、蛋白尿・血尿などを診療対象とする内科です。腎臓は体内の老廃物を排出し、血圧や水分バランスを保つ重要な役割を担っています。腎機能の低下は初期には自覚症状が出にくいため、検診で異常が見つかった際は早めの受診が勧められます。特に糖尿病や高血圧をお持ちの方は、腎臓への影響を受けやすいため、定期的なチェックが大切です。
泌尿器科とは

泌尿器とは、ヒトの腎臓・輸尿管・膀胱・尿道の総称であり、尿の排出をする器官を指します。男性・女性に共通している臓器は、腎臓・膀胱・尿管・尿道ですが、陰茎・陰嚢・前立腺は男性しか持っていない臓器です。泌尿器科は男性・女性問わず、受診が可能な診療科となります。排尿は乳児から高齢者まで全世代共通の生理現象です。プライバシー配慮を徹底していますので、恥ずかしがらずにお気軽にご相談ください。
腎臓内科でよくある症状
- 蛋白尿
- 血尿
- むくみ
- 倦怠感
- 高血圧
- 貧血
- 多尿
- 乏尿
- 夜間尿
- 腰の痛み
- eGFR低下
- 検診異常
泌尿器科でよくある症状
- おしっこが出ない
- おしっこが出にくい
- おしっこの勢いが弱い
- おしっこの回数が多い(頻尿)
- おしっこが残っている感じがある(残尿感)
- おしっこに血が混じる(血尿)
- 尿潜血陽性を指摘された
- 睾丸が痛い
- 睾丸が腫れている
- おしっこするのが痛い(排尿痛)
- 勃起しなくなった
対応疾患
前立腺肥大症

前立腺は、前立腺液を分泌して精子に栄養を与える役割を担っており、膀胱の下で精管・尿道を取り囲んでいます。前立腺肥大は主に加齢が原因で起こります。前立腺肥大によって尿道・膀胱が圧迫されることで、排尿困難・尿が出るまでに時間を要す・頻尿などの症状が起きます。中高年の男性で、排尿に関するお悩みをお持ちの場合、前立腺肥大が関係している可能性があります。何か気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。
尿路結石

尿管結石とは、腎盂から尿管へ移動することで尿管閉塞が起こり、背中・脇腹・下腹部・腰に激痛を伴う病気です。結石とは、尿の成分であるシュウ酸カルシウム・尿酸・リン酸カルシウムなどが固まって生じたものです。結石は大きさによって痛みを伴わないこともありますが、血尿・頻尿・排尿痛・発熱・吐き気・嘔吐などが起こることもあります。痛みがないために結石が詰まった状態を放置していると、腎機能障害を起こすことがあるため結石は取り除く必要があります。治療は結石の発症時期・位置・大きさを確認するため、CT検査・X線検査などの画像検査を行ってから行います。
尿路感染症
尿路感染症とは、尿道炎・膀胱炎・腎盂腎炎・前立腺炎などに分類され、尿道から細菌・ウイルスが侵入することで炎症を起こす疾患です。一般的に身体の構造上、男性よりも女性の尿道が短いため、尿路感染症になりやすい特徴があります。尿道炎・膀胱炎は排尿痛・頻尿・血尿などの排尿に関するトラブルが起き、腎盂腎炎・前立腺炎・精巣上体炎では発熱・背部痛・下腹部痛・精巣の痛みが起こります。女性の方が尿路感染症に罹りやすいものの、前立腺肥大の患者様も発症する可能性が高いため、注意が必要です。
精巣がん
精巣がんの発症ピークは20~30歳代と若年層に多いものの、発症率は10万人に1人程度とされています。初期症状に精巣の腫れ、痛み・精巣のしこり・精巣のサイズが左右異なる・精巣が以前と硬さが違うなどがあり、他にも下腹部痛や違和感などがあるため、いつもと違うと感じた場合には早めに泌尿器科を受診することをお勧めします。精巣がんは、早期発見で完治の可能性が高まる病気である一方、転移することもあるがんです。なお、男性不妊症の方はOnco-TESEという精子温存の特殊な手術が必要になることがあります。未婚の方は妊孕性温存のための精子凍結・手術時のOnco-TESEを行うことがありますので、その際は、適切な施設を紹介させていただきます。
腎盂腎炎
腎盂腎炎とは、尿道から膀胱に細菌が侵入して腎臓にまで細菌感染した状態です。尿道に結石がある、狭窄があると感染リスクが高まります。尿汚染や上気道に異常がないものの尿の汚濁・血尿・排尿痛・高熱・背部痛などが起こり、発熱した場合には腎盂腎炎が疑われます。腎盂腎炎は、放置することで敗血症を起こし、命を落とす可能性があります。糖尿病の併発や膠原病の治療でステロイドを服用している場合は重症化の可能性があります。血液検査などを行い、必要と判断されれば入院して治療を行います。
膀胱がん

膀胱がんは、女性に比べて男性の方が約4倍発症の頻度が高いとされ、45歳以上が95%~、65歳以上が80%と年齢層が高い特徴があります。痛みがないにも関わらず血尿が出ます。最大のリスク因子は喫煙であり、非喫煙者より2.5倍リスクが上がります。芳香族アミン、多環芳香族炭化水素なども原因といわれています。確定診断と病気診断を兼ねて腫瘍を内視鏡で切除します。転移した場合は抗がん剤での化学療法、免疫チェックポイント阻害薬で治療します。術後の再発予防にBCGを膀胱内に注入することもあります。健診で尿潜血が認められ、血尿がありましたら早めに当院までお問い合わせください。
性感染症
主に性行為によって感染する疾患の総称です。クラミジア感染症・HIV感染症・淋病・尖圭コンジローマ・性器ヘルペス・梅毒・毛ジラミ症があり、オーラルセックスでも感染します。排尿痛・血尿・残尿感・尿道から膿が出るなどの症状が起こり、性器の痒みやイボができることもあります。性感染症は、パートナーへの2次感染の他に不妊症・母子感染になる可能性があるため、注意が必要です。性感染症と診断された場合、パートナーの方にも検査を受けていただくことをお勧めします。
膀胱炎
膀胱内が細菌感染することで炎症を起こし、急性膀胱炎では排尿痛・頻尿・残尿感・血尿などが起こります。糖尿病が原因の場合は、 自覚症状がないこともあります。抗菌薬で適切な治療を行うことで完治が可能です。水分摂取や痛みがあってもトイレを我慢しないことが大切です。細菌には薬剤耐性菌も存在し、尿培養の薬剤感受性を調べて正しい抗生物質を使う必要があります。治療を中断することで再発のリスクが上がり、完治に時間を要します。医師の指導の下、尿がきれいになっていることを確認して治療を継続することが大切です。膀胱炎予防のために、日常的に水分補給と排尿を我慢しないようにしましょう。
過活動膀胱
膀胱内に尿が溜まっていないのに、膀胱が過活動になり頻尿になる状態を指します。水の音で尿意を催す・トイレに入ると激しい尿意を催すなどが起こり、尿意を我慢できずに失禁してしまうこと切迫性尿失禁を併発することもあります。加齢・ストレスによる自律神経の乱れ・膀胱の知覚過敏などの原因が重なって発症します。日本では40歳以上の約12%が過活動膀胱で悩んでおり、日常生活にも影響が出るため適切な治療が必要です。患者様の状態に合わせた薬物療法・適量飲水指導・骨盤底筋群のトレーニング・膀胱訓練などのアドバイスを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
当院で可能な検査・治療
- 尿検査(一般・沈渣)
- 血液検査(腎機能、感染など)
- 腹部エコー(超音波)
- 残尿測定(エコーによる)
- CT検査(腎・尿路の詳細評価)
- レントゲン検査(尿路結石の確認など)
- 前立腺超音波
- 尿培養検査(感染菌の特定)
- PSA検査(前立腺腫瘍マーカー)
- 内服薬処方(抗菌薬・排尿改善薬など)
- 生活指導(食事・水分・排尿指導)
- 漢方薬治療(体質や症状に応じて)
- 前立腺肥大の薬物治療
- 過活動膀胱の治療(抗コリン薬など)
- 尿失禁の治療(薬・骨盤底トレーニング)
- 膀胱炎などの感染症治療
- 結石の排出促進・再発予防治療
- 点滴治療(脱水、感染など)
- ED治療(勃起障害用の薬)
- 腎機能管理(慢性腎臓病に対して)
健康診断の結果が
気になったら
健康診断や人間ドックの結果で「尿タンパク」「血尿」「クレアチニンの上昇」「eGFRの低下」「血圧が高め」などを指摘されることがあります。これらは腎臓の機能や泌尿器系の異常を示している可能性があり、放置すると将来的に大きな病気へと進行するリスクもあります。
特に腎臓疾患は初期には自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに悪化することが多いため、早期の受診がとても重要です。また、尿に関する異常や排尿トラブルも、日常生活に支障をきたすことがあります。
当院では、健診で異常を指摘された方への再検査や専門的な評価、今後の予防に向けた生活指導まで幅広く対応しています。
「症状はないけれど気になる数値がある」「どこに相談すればよいか迷っている」といった場合も、ぜひお気軽にご相談ください。
担当医師
医師
秋山 昌範 Masanori Akiyama
経歴
- 1983年3月 徳島大学 卒業
- 厚生技官・MIT客員教授など歴任
- 医学博士
専門領域
- 腎臓内科・泌尿器科
- 総合診療科
- 心療内科
資格
- 日本腎臓学会専門医
- 透析医学会透析専門医
- 難病指定医(腎臓病)